前回もお伝えしたように、目の前にある、今ある共同体や関係の中に適応しなければならない、適応できない自分はダメだ、適応している人はすごい、と、私たちはつい幻想にとらわれてしまいます。
実はそうではない。
(参考)→「適応できることがいいことではない~“不適応”というフィードバック」
自分はあの会社ではうまくいかなかったが、他の人(例えばAさん)はうまくやっている(だから自分はダメだ)
他の人はあのグループで仲良くやれている、でも自分は馴染めなかった(だから自分はダメだ)
と思いがちです。
私たちは、実験を重ねるようにして、ここが合わない、ここも合わない、と試行錯誤(不適応)しながら、自分の道を見つけていきます。
人はどんどんと共同体を移動していくものです。
もともといた共同体に属し続け(うまくやり続け)なければいけないというのは幻想でしかありません。
特に、生まれた場所、地域だからそこが自分にとって良い場所(故郷)とも限りません。
地方などは典型的ですが、閉鎖的で、同調圧力が強い地域もよくあります。
さらに、そんな場所から、卒業したり、抜け出したりして、自分の道を見つけていく際は、決して、キレイに移行、卒業できるというわけではありません。
例えば、中学や高校で、つるんでいた友達と離れて、勉強や部活に熱心になったら、「あいつは付き合いが悪い」と言われて陰口をたたかれることになります。
自分のやりたいことを見つけて進む中では、地元の友達関係とは距離を取ることになります。
その際も、「あいつは変わった」「何、調子に乗ってんだ!」と悪口を言われるかもしれません。
生まれた地域も同様です。
地元の消防団などの会合や、寄合には出ないという選択肢を取ったり、転居したりする。「あそこの家の娘、息子はおかしい」「付き合いが悪い」と言われるかもしれません。
会社も同様です。
「あいつは仕事ができない」「あいつは使えない」と言われたりします。
パートナーとの付き合いも、別れるときはものすごいストレスがかかります。相手から罵倒されるかもしれません。
問題のある父や母、親族とは距離を取らなければなりません。その際にも、とても嫌な呪いの言葉を浴びるかもしれません。 強い罪悪感、自責の念を感じる。
そんなストレスを経ながら私たちはところを得ていきます。
それぞれから離れる際には、
「なんで、あんな態度をとってしまったのか?」
「うまいことを言っておけばよかったのに。私は本当にバカだ」
「ほかの人ならうまくやれた(自分はうまく付き合えなかった)」
なんて、自分の不器用を呪うこともあります。
これらは、すべて「不適応」です。
しかし、「適応しなければ」と、中にはその不適応から生じるストレスを避けたいがために、あるいは「すべての場所で適応しなければならない」「過去に失敗したから今回は同じことはできない(同じようにケンカ別れになったら、自分だダメな人間であると確定されてしまう)」「すべての環境、人から合格点をもらえなければ、次に進んではいけない」という間違った観念、幻想を元に、適していない環境に居続けてしまう、というケースがあります。
まさに”適応幻想”による呪縛と言うしかありません。
私たちは、どんどん環境を変え、移動を続けていくものです。
そうやって人生を作っていきます。
家族にも良い子と呼ばれ、今でも地元の友達とも付き合いがあり、人生で出会うあらゆる人から好かれ、地域でも覚えがめでたく、勤めた会社では惜しまれて転職、なんて、そんなことは実際にはあり得ません。
いつも旅行やグルメを楽しんでいる姿をアピールするようなYoutubeやインスタと同じくらい作られた幻想です。
もし実際に、うまくやり続けてきたとしたら、「何かがおかしい(本当の自分が殺されていないか? ほかの人や何かを犠牲にして成り立っていないか?)」と見ないといけません。学歴もキャリアもプライベートもうまくいっているように見える人が実際には本当は自分の人生を歩んでいない、という例はとても多いのですから。
共同体にとっては自分たちの共同体の正統性を維持するために、脱退されることを防ぐためにも逸脱する人を悪く言うという動因もあります。
そんな恐れから、共同体にとどまったりしてしまってはいけません。
そして、悪く言われることをもって、自分がダメな人間だと思うことも必要ありません。仲良くできるのも、無用なあつれきを賢く避けることも、もちろん愛着(生きるため)の力ですが、時に仲違いをしたり、必要なけんかをすることも、生きていくのに必要な力です。
そうして必要な際は腹をくくり、自分の気質、持ち味が持つ、必要な流れに沿って、更新し続けることこそが大切なのです。
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ


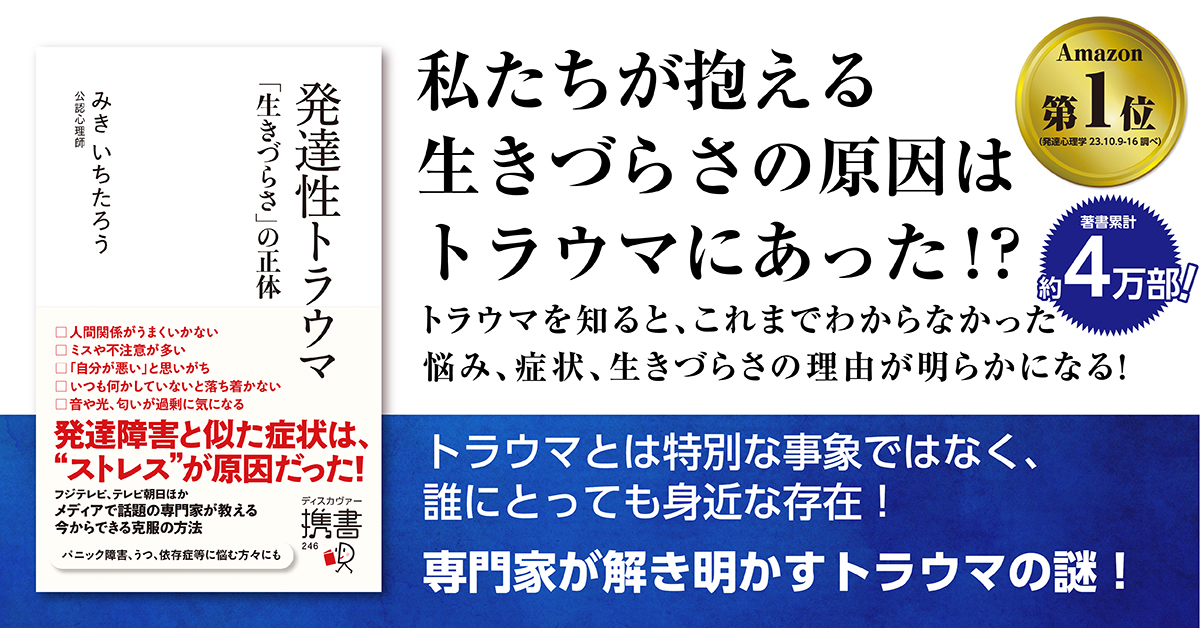
コメントを投稿するにはログインしてください。