人に対するイライラで、頭がぐるぐるすることがあります。
「もっとこうするべきでしょ!」とか、
「本来は、~~であるはず!」とか、
その「理屈」は、自分の中では完璧で、それが通らない相手は極端に言えば人間として認められない、くらいに相手を否定したくなります。
さらに、「理屈」を重ね、頭の中でシミュレーションを走らせてしまいます。
でも、いくらそうしても、イライラはさらに増すばかりで解消されることがありません。
実際に、相手に怒りをぶつける場合もあります。
説教のようにくどくどと相手に「理屈」を伝えますが、イライラはエスカレートしていきます。
さらに、相手はそれで「理屈」を理解して、同じ行動を取らないのか、といえばそうではなく、逆にまた同じくこちらの神経を逆なでするようなことをする。
「同じ行動をするなんて、どういうこと!?」とまたイライラして怒りをぶつける。
こういう繰り返しに陥っている、というケースはよくあります。
いくら「理屈」を展開して、相手をねじ伏せようとしても、相手に伝わることはありません。
なぜなら、その「理屈」はイライラしている本人のものではないから。
ほとんどの場合は、自分の両親や生まれてきた中で出会った他者の価値観を内面化(直訳)したもので、自分のものではありません。
目の前の刺激をきっかけに解離して、「理屈」の世界に頭が持っていかれている状態。
イライラ自身も、生育歴で得たストレスの投影なので、実は現在のものではなく、過去からくるイライラだったりする。
そのため、イライラされている相手も、無意識にそのことをキャッチしていますから、
「イライラされていて怖いけど、よくみたらそれは自分の責任ではないし・・」と感じています。
展開される「理屈」も
「正しそうに見えるけど、状況にマッチしていないし、言っている本人のものになっていないし・・」と直感しているのです。
だから、イライラと「理屈」をぶつけられても、行動を変化させる謂れはないのです。
イライラしている本人は、実は、生育歴で得たストレスと、親などのローカルルール(「理屈」)に巻き込まれていて、自他の区別を失っている状態です。
本人は全くの正論を展開しているように見えて、実はそれは自分のものではなく、状況にマッチしたものではなかった。
「理屈」を考えれば考えるほど、自他の区別を失い、自分の感情と価値観で生きることからは離れていってしまうのです。
(参考)→「「察してよ!」で、自分の主権、主体性が奪われる」
さらに、「理屈」で頭が持っていかれて自他の区別を失っていると、他人が展開した「理屈」(ローカルルール)にも巻き込まれやすくなります。
不全感を解消するために他者に因縁(「理屈」)をつけて、その「理屈」の世界でごちゃごちゃとやり取りするようなことに慣れてしまう。
「理屈」で考えることが当たり前になりますから、「物理的な現実」からも離れやすくなる。ありのままにある現実に立脚することが自然とできなくなるのです。
(参考)→「“作られた現実”を分解する。」
「物理的な現実」としての自分ではなく、「理屈」で作られて自分で生きることになるため、他人が作ったイメージや評価、言葉にも振り回されやすくなります。
まさに、ブッダが悩みの原因とした「執着」の世界です。
こうした状況から逃れ、自他の区別をつけ、ローカルルールではなく、物理的な現実の世界に立ち戻るためにはどうしたらいいのか?
それが、前回お伝えした「理屈」をつけず「感情」をそのまま感じるトレーニングです。
(参考)→「感情は、「理屈」をつけずそのまま表現する~自他の区別をつけて、ローカルルールの影響を除くトレーニング」
「理屈」は被せずに、ただ、自分の感情を感じて、それを表現する。
それをずっと繰り返します。
すると、自分がいかに自分のものではないものに支配されてきたかが、明確になってきます。
徐々に自他の区別がついてくる。
「理屈」に頭が持っていかれて、ぐるぐるとすることが減ってきます。
さらにパート2の応用編としては、
「認知」と「思考」とを切り離すということも行っていきます。
たとえば、
道を歩いていたときに、気になる人がいて、「なんだ、変な人だな」と思う状況があったとしたら、
意識して、「認知」と「思考」を分けます。
「男性が歩いているのを見た」(認知)
「なんだか変な人だな、と思った」(思考)
というふうに。
別の例では、
信号が赤になって、「しまった!信号に捕まった」と思う状況に出会ったら、
「目の前の信号が赤になった」(認知)
「しまった!と思った」(思考)
というふうに。
これを繰り返して、 「認知」と「思考」を分けていくと、漫然と自他の区別なく、環境に巻き込まれるようになっていたことがなくなり、自分の認知や感情が明確になってきます。
「そういえば、このせっかちさは、父に怒られたからだな。」「父はせっかちで、いつも車の運転で赤信号になったら舌打ちしていたな」といったことに気がついたりもします。
「あっ!自分の考えと思っていたものは、父の価値観だったんだ?!」と気がつくようにもなってくるのです。
(参考)→「内面化した親の価値観の影響」
さらにローカルルールの影響から離れ、自他の区別が明確になってきます。
(参考)→「ローカルルールとは何か?」
●よろしければ、こちらもご覧ください。

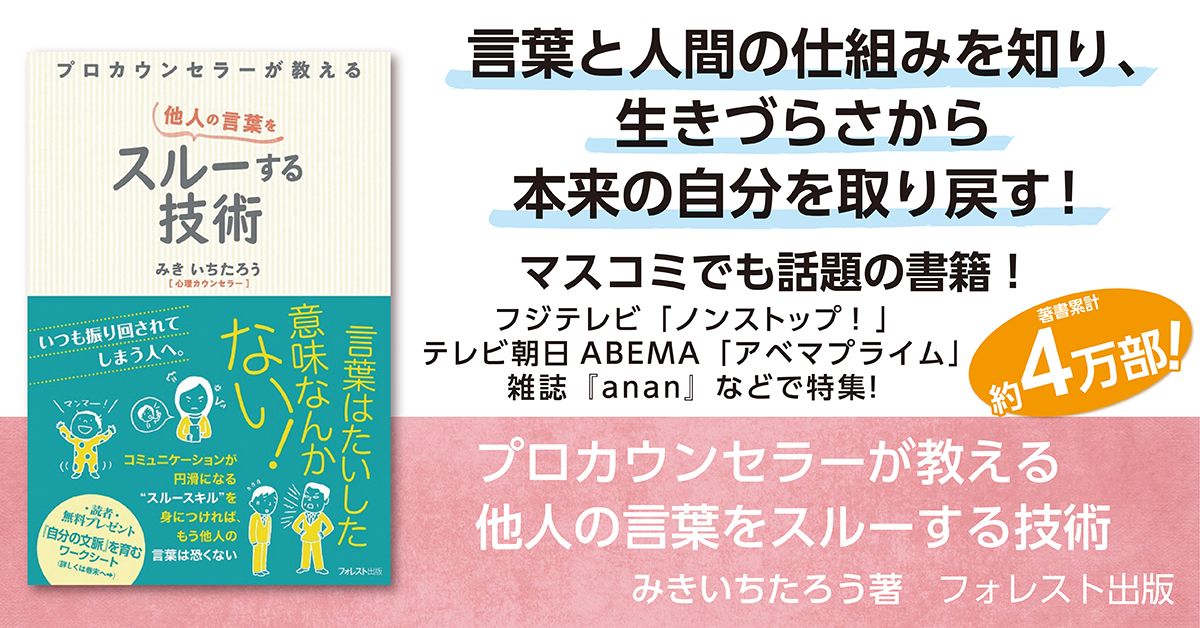





コメントを投稿するにはログインしてください。