ローカルルールにかかってしまうと、ハラスメントを仕掛けてきている人、支配してきている人に相談しようとする、関わろうとするという悪循環に陥ることがあります。
(参考)→「ローカルルールとは何か?」
ハラスメントを仕掛けてきている相手ですから、嫌なことを言われるに決まっているのですが、何故かその人に相談してしまう。
「私は大丈夫かどうか?」「これはどうしたらいいの?」と尋ねてしまう。
親や家族などが典型ですが、特に問題が起きると、そのハラスメントの加害者に相談する。
傍から見ていると「なぜ、問題の原因になっている人に、自分を苦しめている人に声をかけるの??」と思ってしまいます。
詐欺に引っかかった被害者の方が、詐欺だとわかったあとに、加害者である営業マン(詐欺師)を呼んで、「これはどうしたらいいですか?」と相談するようなことが起こりますが、まさに同様の事象です。
相談するなら消費者センターとか、弁護士とか、警察であるはずですが、なぜかそこには相談しようとしない。
なぜか外の人を警戒し、家(内)を守ろうとしてしまう。
外の専門家に相談したらいいのに、身内に相談してしまう。
あるいは、外の専門家に相談するのも先延ばしにして、自分の頭の中でもやもやと考えて時間を浪費する。
(参考)→「外(社会)は疑わされ、内(家)は守らされている。」
どうしてこのような事象が生じるのでしょうか?
色々と要因はありますが、一つには、尋ねる相手が自分の存在を承認してくれると期待しているためです。
あるいは、自分が関与を続けないといけないと思っているためです。なにか自分の不安から逃れるためです。
もう一つは、ニセの公的領域(≒私的領域)に絡め取られていて、本当の公的領域にアクセスすることができていないためです。
(参考)→「ローカルルールと常識を区別し、公的環境を整えるためのプロトコルを学ぶための足場や機会を奪われてきた」
まさに依存関係にあるということです。これは頭では切り替えることができない。体験や経験を偽装されているので、身体レベルでニセの公的領域が現実であると思わされています。
最後には、コミュニティや社会自体の力も十分ではないということもあります。
これは、日本の近代社会、現代社会の特徴でもありますが、コミュニティの力が弱く、行政の目も粗いために、私たちの側にそれを利用する能力やリテラシーがないと、社会の中で自分を位置づけること、社会の資源の利用が難しい、ということがあります。
いろいろな問題はありながらも、うまくアクセスができれば何とか生きていけるだけの資源が社会にはあります。しかし、そこにたどり着けないままこぼれ落ちることも多い。
上の例でしたら、行政や警察などに相談したってどうせ良い対応が返ってこない、カウンセラーに相談しても理解してもらえない、頼りない、という経験をしてしまっている。
実は、「相談」や「探索」という行為自体が飛び込み営業、新規開拓にも似て、とてもエネルギーがいることです。
こちらに自尊心が一定以上ないとくじけてしまうことでもあります。
ですから、自尊心のエネルギー残量が一定以上に低下したり、相談や情報収集のスキルが十分ではないと、よい資源にアクセスできる前にくじけてしまう。
本来の社会、コミュニティはそうした人でも包摂するように設計されなければならないのですが、現時点の日本社会はそうはなっていません。能動的にアクセス、探索が必要な段階の社会です
(もっと言えば、”家族”という社会の最小単位足りえないものを基礎として設計してしまったおかしな社会。だから、まずは「家族」に相談してしまうのです)。
(参考)→「自分のIDでログインするために必要な環境とは」
本来、生きづらさとは社会からもらされるものですが、トラウマを負うと、社会の仕組みの不十分な点を内面化してしまい、抱えてしまうようになります。
その結果、特に「家族」という脆弱なものに頼らざるを得なくなり、家族の機能不全や依存関係の影響にからめとられて行ってしまうのです。
その結果、ハラスメントの加害者、あるいは、機能不全の家族に”相談する”なんていう滑稽な現象が生じるのです。
詐欺師に相談することをもって、本人のせいだ、というのも実はかなり酷なことなのです。本当は構造の問題です。
トラウマの特徴の一つはハラスメント(心理的な支配)、なのですが、トラウマを負わされていると、このような構造が生じます。
みきいちたろう『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』(ディスカヴァー携書)
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

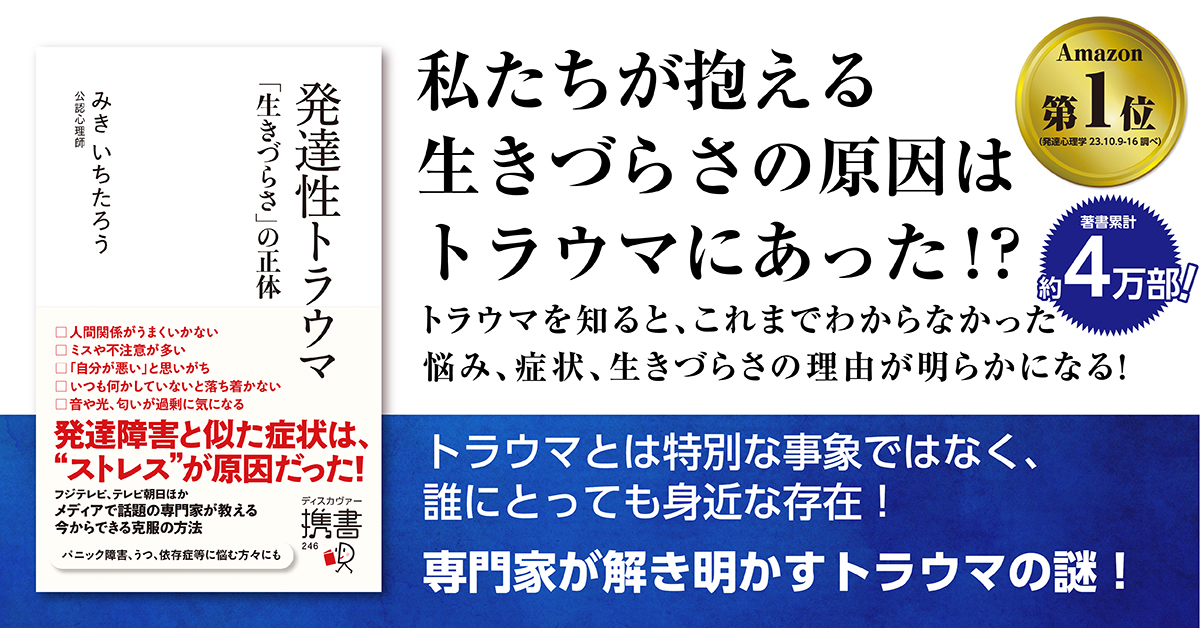

コメントを投稿するにはログインしてください。