私たちの周りには実は神話、虚構にあふれています。
例えば、
「あの人はしっかりしているから、そんな事を言うとは思えない」とか、
「あの人は、会社では評価されているし、友達も多いから、あの人の言うことは間違いない」とか、
「学歴が良くて、良い会社に言っているし、部長にもなれているから成功者だ」とか、
反対に、自分に対しても虚構は存在します。
「こんな失敗をする自分は、よほどだめに違いない」とか、
「あんな発言で人を傷つけてしまった自分は罪深い」とか、
「親との関係がうまくいっていないのはだめなことだ」とか、
実は、こうした、自分はだめだ、とか、あの人はうまくいっている といったことは、わずか数点の情報から成り立っているだけの虚構に過ぎません。
数点から成り立つものを、心理学ではヒューリスティックといいます。
私たち人間は、現実の全てを認識することはできません。
日常において全ての事象に対してそれだけの処理力はないし、全てに対してありのままの処理をしていまうとパンクをしてしまいます。
だから、数点の情報から判断しようとする性質があります。
ヒューリスティックとは、そうした意識の省力化のことです。
神話や虚構というのは、その数点の柱を操作されてしまうことによって生じます。
たとえば、友達グループの中で、人望がある、成功している、とされる人が「まともだ」というのも単に、いくつかの情報で判断している。
・割と立派な会社に努めている
・いつも、落ち着いて発言する
・友だちもいる
だから、あの人はまともだ
など
でも、実際その人がまともかどうかなどは全くわかりません。
事実、DVの加害者などは、上記の特徴に全て当てはまったりします。
(参考)→「DV(ドメスティックバイオレンス)とは何か?本当の原因と対策」
不祥事を起こす有名人たちなども、上記の特徴を満たしたりしていますが、実際蓋を開けてみると、その各条件を維持するために、周囲が犠牲を払っていることもしばしば。
本人がその負担に耐えかねて、おかしな行動を取る、なんてこともあります。
「ベストマザー賞」「ベストファザー賞」を受けた有名人が続けて不祥事を起こしていることが話題となりましたが、それなども、仮にも賞はだれかが選考していて当然なにかの情報から選んでいるわけですが、まさに虚構を掴まされているわけです。
東大などの学歴があるということの背景には、幼い頃から、かなり窮屈に塾通いをしていて、ある種の歪みを抱えてしまっている人もいます。
本当にオーガニックに頭がいい人いうのは稀で、だいたい、その領域で良い成績を取るための文化に過剰適応をしてしまっていて、融通が利かなくなってしまう代償を払うことも生じます。
そうしたことへの違和感を書いたのが、例えば、東大の安冨歩教授が書いた「東大話法」に関する本などです。
東大話法というのは、事務仕事などについてバランス感覚に優れたとされる東大出身者たちが発する、現実を歪める歪な会話や立場主義やを批判したものです。
成功者やエリートとされる人たちも、ある種の歪みの上に成り立っていたりします。
おごれる平氏も久しからず、ではありませんが、うまくいっている、ように見える状態と言うのは、ある一定の条件下で可能になっているだけでしかありません。
とくに、水面下の水かきは世間には見えず、華麗な一面だけしか表には出てきません。
スポーツ選手など、華麗なプレーの背景には、日々の努力があり、引退してからはもう競技に触れたくない、と言う人も少なくありませんし、プロになった時点ですでに、もうその競技に飽きていて、うんざりしている、なんてケースも珍しくないようです。
学生時代に輝いていた人、成績の良かった人に、あとで話を聞いたら「当時は結構大変だった・・」なんていう裏話を聞くことなんていうのも珍しくありません。
学生時代にみんなから頼りにされていた人が、実は、アダルトチルドレン状態の結果「しっかりしている子」になっていただけ、ということもよくあります。
経営者も、現役時代は華麗な業績を上げていても、実はそれは不正のためだったということもあります。
資本主義というのはレバレッジを特徴としており、ブラック企業とされるくらいにおかしな企業でも上場するまではいきますし、大企業であれば、おかしな経営をしても5~10年は良い業績を出すことは普通にあるのです。アメリカのGEや日本の日産、ビックモーターのように、のちに問題が明らかになったりします。
(さながら、ある特定の栄養素だけを接種したり制限をする単品ダイエットのようです。栄養のバランスを崩せば人間はダイエットに一時的に成功しますが、それは本当のダイエットでも何でもなく、その代償を後に払うことになりますがそれと同じです。)
でも「ほら、あの会社はうまくいっている、あの人はうまくいっている(なのにお前は)」と言われたら真に受けてしまう。トリックでしかありません。
さらにいえば、そもそも、人間がまともだ、ということ自体が虚構です。
ある一定の条件下でかろうじてまともに見えるのが人間というものです。
このことは『プロカウンセラーが教える 他人の言葉をスルーする技術』(フォレスト出版)で書かせていただきました。
人間は社会的な動物ですが、足場に多様性を欠き、ローカルな環境に過剰適応をしてしまうと、「しっかりしていて、まともにみえるけども(実はおかしい)」という状態に容易になってしまうのです。
一方、虚構は自己評価にも向いています。
・自分は今働いていない
・友達も居ない
・上手くコミュニケーションが取れない
だから、おかしい
など
ほんの数点のことで判断させられてしまっている。
これなども虚構です。
ちょっとゴールポストを動かされてしまえば、数点の柱などを揃えることなどは造作もありません。
そうして幻惑されると、「だめな自分」の完成です。
一旦成立してしまうと、自尊心も失われてしまいますから、失敗を繰り返すことになります。
そうして、虚構は何がしかの説得力のある”証拠”で固められて、事実のように思わされてしまいます。
(参考)→「“作られた現実”を分解する。」
トラウマが長引く場合は何が原因かといえば、こうした虚構、神話があって、そのもつれ具合、絡まり具合がその主要な要因としてあり、それをほぐすのに時間がかかるということが背景にあります。
虚構や現実は、前回の記事でお伝えしたような複数箇所でのハラスメント経験で強固なものとなります。
(参考)→「複数箇所での常識を揺るがされるハラスメント経験」
多くの場合、本人も、虚構だとは思えず、思うことじたいが「逃げ」「都合の良い解釈」「ピンとこない」として放棄されていることも珍しくありません。
今回しているような「虚構、神話」についてお伝えしても「たしかにそうですが、でも、私はダメなんです」として無意識に流されてしまうということが生じます。
みきいちたろう『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』(ディスカヴァー携書)
●よろしければ、こちらもご覧ください。

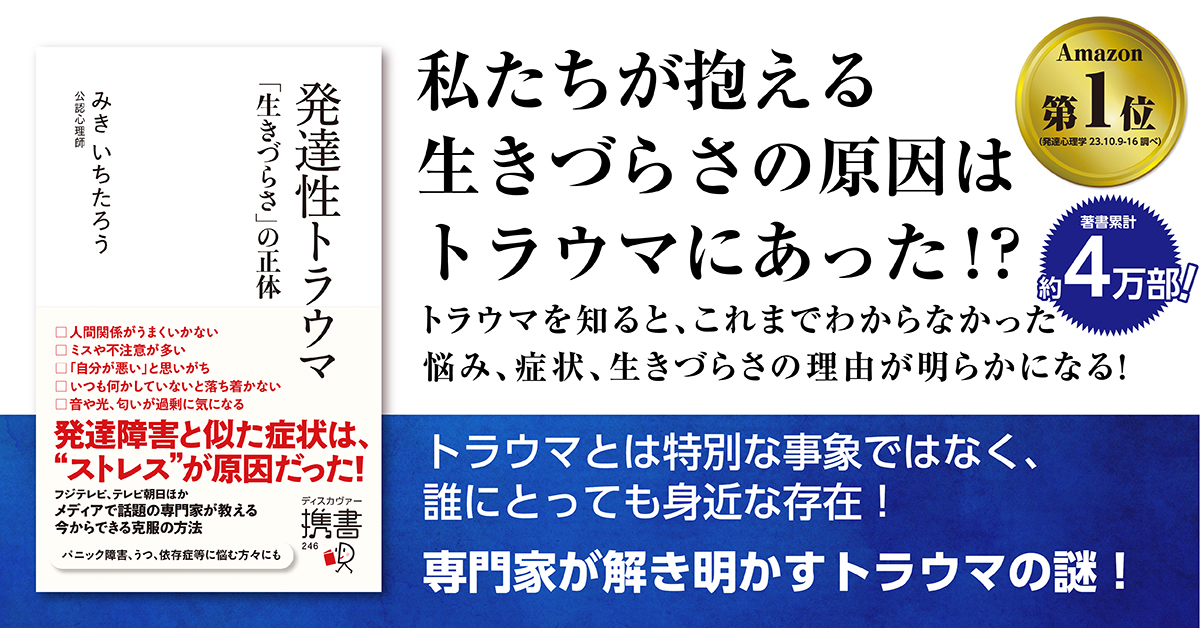

コメントを投稿するにはログインしてください。