アラン・ソーカルという物理学者が、1996年に「境界の侵犯:量子重力の変換解釈学に向けて」という論文を雑誌に掲載しました。その内容を見て、批評家や思想家たちが評価しました。
一通りの評価が揃ったころに、その頃合いを見計らって、実はその内容は哲学や物理学の単語をもっともらしく並べただけの全くのデタラメだったと発表しました。意味のない文章を見て「意味がある」と評価した学者や批評家は面目丸つぶれになりました。
アラン・ソーカルは、現代思想などで科学の知識がいい加減なまま乱用されていることへの警鐘として、こうした挑発を行ったといわれています。
「アラン・ソーカル」事件といいます。
実は学者とか専門家でも、自分の目で見て、頭で考えて物事を判断しているわけではなく、「すごそうだ」とか、「すごいといわれている」ということで判断をしているのではないか、というのです。
昔は、日本でもマルクス主義という考え方が主流でしたが、今から見ると非科学的な考えも含まれていますが、「真理である」と普通に流通していたりしていました。
それも、当時の社会状況や問題意識もありますが、じつはベタに言うと「(内容はよくわかってないけど)なんか、すごそうだ」というような感情がベースにあったのではないかと考えられます。
もう亡くなってしまいましたが、吉本隆明という思想家がいました。娘は吉本ばななという作家です。「戦後最大の思想家」と呼ばれ、信奉者も多い人です。
近年は、それに対して疑義を唱える人が出たりしています。
「吉本隆明という共同幻想」という本がありますが、簡単に言えば、「吉本隆明というのは、難しく書いてあるだけで、何を書いているのかわからない。実は内容も意味がないのではなかったのではないか?!」
というものです。単なる難癖ではもちろんなく、吉本のいい加減な言葉遣いや、デタラメさについて、細かく例を上げて示しています。
かんたんなことをわざわざ難しそうに書いてあるのは、結局は、「どうだ、オレはすごいだろう!」という顕示欲や相手をマウンティングしたいという支配欲だったのではないか、というのです。
その難しそうな文章を見て、同時代の人たちは「吉本隆明はすごい」と思って、共同幻想(ローカルルール)に染まっていただけではなかったのか?と。
明治大学の鹿島茂教授が、小林秀雄を取り上げて同じようなことを書いています。
小林秀雄といえば、私たちが使っていた国語の教科書にも登場する日本を代表する英文学者とされます。
しかし、小林秀雄もどうやら「どうだ、オレはすごいだろう!」という自意識から、わざわざ難しい言葉で文章を書いていたのでは?というのです。

鹿島茂は、
「小林秀雄が書いた文章で「わかった!」と思った経験が一度もない。文の一つ一つが理解不能である。また、文の一つ一つのつながりもよくわからない。」
「昔は、わからないのはこちら頭が悪いのせいだと思っていたが、今になると悪いのは小林の文の方であることがわかる。」
「こういう意味不明なことを書く小林秀雄も困ったものだが、それを入学試験にあえて出題する大学教師とは一体どういう神経をしているのだろうと疑った」
作家の丸谷才一や、比較文学者の小谷野敦も小林秀雄は意味不明だと批判しているそうです。
でも、小林秀雄は国語の教科書にも載っているくらいだから、それなりの学者たちには評価されていたはずですが、実は、それは、「どうだ、オレはすごいだろう!」というローカルルールに染まった結果だったのかもしれない。
そのことを、鹿島茂は、漫画家東海林さだおの言葉を借りて「ドーダ」という言葉で表現しています。
「ドーダ」とは、「自己愛に源を発するすべての表現行為である」と定義しています。
(なんか、ローカルルールとよく似ていますね)
(参考)→「ローカルルールとは何か?」
本当はすごくないけども、皆が何故かすごいと思いこむのは、「その時代特有の「集団の夢」」だと鹿島茂は言っています。
さらに、森鴎外や、西郷隆盛などを取り上げて、歴史上の人物の行動にも、「ドーダ」というものがあったとして、これまでとは違って視点で「すごい」とされる人の行動の背景にある「ドーダ」を描いています。
さて、こうしたことから見えてくるのは、「すごそうだ」とか、「皆から評価されている」ということの実像です。

私たちも、「職場のあの先輩は皆から評価されている(でも、私には理不尽なことをする)」「親戚のあの人は尊敬されている(でも、とても支配的で窮屈だ)」ということがあります。
周りから評価されているから、ということで理不尽さを否定し難いように見え、自分を否定する行為を真に受けてしまいがちですが、それも、結局「ドーダ」という集団の夢だったのではないか?別の言葉で言えば単なる「ローカルルール」でしかなかったのではないか。
日常でも、わたしたちに対して、「仕事はここまでできて当然だ!」とか、「これができないなんて恥ずかしい!」と指摘してくる人がいたりしますが、それって、結局は、その人が「自分をすごいと思わせたい」「相手をマウンティングしたい」「相手を負かしたい」という気持ちの発露でしかなかったのではないか。
つまり、「ドーダ」でしかなかったのではないか?
もちろん、「ドーダ」以外にも嫉妬ということもあります。広義では嫉妬も「ドーダ」といえますが。
筆者も、以前の職場で、先輩から「東大卒で営業部に配属されて、上司からいじめられた人」の話を聞いたことがあります。
東大卒ということに対するやっかみから、「こんなこともできないのか」と些細なことを取り上げて上司がその人をいじめて潰してしまった、というのです。
東大卒のその人は、指摘されることが事実であると真面目に考えて、単なる嫉妬でしかないことで潰されてしまったのです。
このブログでも、手塚治虫の有名なエピソードをとりあげましたが、
手塚治虫も、嫉妬から同輩や後輩の漫画家を「こんな描き方はだめだ」こき下ろして、トラブルになることしばしばであったのです。
漫画家の神様も、当たり前ですが、業の深い人間でしかないのです。
(参考)→「人の発言は”客観的な事実”ではない。」
わたしたち人間はだれでも、嫉妬や「ドーダ」から自由ではありません。
鹿島茂は、「ドーダ」は自己愛から発するので、「自己愛とはターミネーター2の金属男のように、あらゆる形をとってどこにでも発言するから、容易にそうとは見抜けぬ」といい、そして、「表現というものは、それがどういうかたちをとっていようとも、ドーダ」ともいっています。
いいかえると、私的領域の言葉はすべてローカルルールということです。
だから、人の言葉や行動をそのまま真に受けるなんてしない。できるわけない。
トラウマを負った状態というのは、いいかえれば「ローカルルール」の幻想にとらわれている状態。ローカルルールの幻想とは、「そうはいってもローカルルールが正しい」「自分は間違っている」という感覚。
だから、代謝が進まない。
でも、そのローカルルールとは、結局「ドーダ(私的情動、不全感)」でしかなかった。
ローカルルール(人格)の言葉とはすべてそうです。
深刻そうにして、相手を非難する。自分は悲劇の主人公で、それを理解できない相手の理解や共感性の欠如に問題があるとする。
難しい理屈で感情や思考をこねくり回して理屈を作り上げているが、意味不明。
しかし、ローカルルールというものの正体がわかると、
「文の一つ一つが理解不能である。また、文の一つ一つのつながりもよくわからない。」
「昔は、わからないのはこちらのせいだと思っていたが(罪悪感を感じていたが)、今になると悪いのはローカルルールの方であることがわかる。」
のです。
もっと別のケースでわかりやすく言い換えたら、
「昔は、親の言うことが、わからないのはこちら頭が悪いのせいだと思っていたが、今になると悪いのは親の方であることがわかる。」
あるいは、
「昔は、友人やパートナーの言うことが、わからないのはこちら頭が悪いのせいだと思っていたが、今になると悪いのは友人やパートナーの方であることがわかる。」
そして、親や友人やパートナーの言うことに賛同していた人たちは、「集団の夢」に染まって、
「こういう意味不明なことを言う親や友人パートナーも困ったものだが、それに賛同する人たちとは一体どういう神経をしているのだろうと疑った」
ということです。
「生きづらさ」とは、結局、他人のドーダを真に受けて、後始末を押し付けられている状態、といってもいいかもしれません。
(参考)→「あなたが生きづらいのはなぜ?<生きづらさ>の原因と克服」
実は、冒頭のアラン・ソーカル事件のように、人間というのはローカルルールの世界では中身などは見ていないのです。「なにやらすごそうだ」という様だけを見て、それなりの人でも、おかしな理屈に染まったりする。
ドーダはあちらこちらにありますから、そうと知っていなかれば、ついついもっともな気がしてしまいます。そして、自分が特別に駄目だと思ってします。
歴史に名が残るような人、あるいは現在すごいとされている著名な人でも、結局は意識、無意識にドーダをかましているだけ可能性が高い。
というか、鹿島茂が「表現というものは、それがどういうかたちをとっていようとも、ドーダ」といっているように、すべての言動はドーダなのだと思う必要がある。
特にテレビとかマスコミに出るような人は、全てが演出でできていますので。
スポーツ選手も、経営者も、作家も、政治家も、哲学者も、芸能人もみんなみんな「ドーダ」でできていただけだった。
身近な人達なども同様です。
カーネギーの名著「人を動かす」はまさに、「ドーダ」の塊である人間をどう扱うか?をまとめた本でした。
日常生活において、例えば仕事で威圧的な人にあったら、「あ、この人もドーダなんだ!」と考える。
「このくらいのこともできないの」といわれたら、「あ、この人、今ドーダをかましてきた」と気づく必要がある。
(昔、アニメとかで見た、見栄を張った奥様同士の会話のようですね。「うちの主人は、今度ニューヨークに出張なんですのよ!」のと同じこと)
「自分はできていない」「自分はだめだ」なんて、反省したり、真に受ける必要なんてありません。
みんなが「すごい、すごい」と言っていても、「本当か?」と思ってよい。
というか、思うほうが普通だし、世の中を生きる者の作法として、疑わないといけない。
でも、健康な人間はすべてを疑って生きてもしんどいので、ノリつつツッコミ、ツッコミながらノル、ということをして生きる。
二重の意識を持ちながら物事を楽しんだりします。
人間というのは、本来「すごい人」など実は一人もおらず、誰しも業が深く、弱い生き物なのです。
(参考)→「ローカルルールとは何か?」
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ
・お悩みの原因や解決方法について

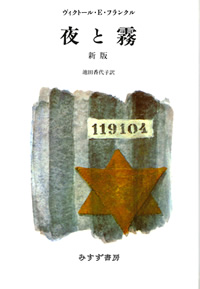


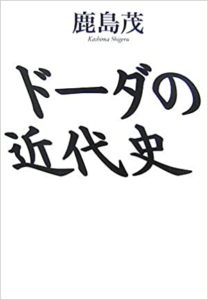
コメントを投稿するにはログインしてください。