クライアントの持つ疑問(ある種の呪縛でもある)としてよくあるのが、「育った家庭環境が悪いのはわかったが、兄弟もいる中でなぜ私だけこんなに苦しんでいるのか?」というものがあります。
これは、もっともな質問であると同時に、その裏には暗に「環境が悪いし、その影響があるというなら、兄弟もすべてが病むならわかるが、私だけそうなるということは、私がやはりおかしいのだ」というトラウマによる心理的な呪縛を伴っている質問です。
これについては以前の記事でも書きました。
(参考)→「同じ環境でも問題が出ているのは自分だけだから自分に問題がある? おかしな環境は優等生を必要とする。」
同じ環境であっても受ける側の気質も状況もポジションも異なりますから、同じようにならなくて当たり前です。
家族の中でも影響に差が出ますし、その中で優等生として優遇される人が出たり、カルト宗教で幹部になるようなごとき間違った適応を果たす人もいる、ということです。
そうしたことに加えてもう一つ、自分だけが病んでいる、ということの理由があります。
それは、その方が家族の中で一番利発でまともであった、ということです。
私たちは景色や見ている画像が揺れたりすると、酔ったり、気持ち悪くなったりしますが、それも、こちらがまともな感覚があればこそです。
おかしいのは揺れている画像のほうです。
反対に、海に揺られていると、揺られていることに適応して、陸に戻っても揺られているような感覚がしたりすることもあります。
こうした自然環境だけではなく、社会環境に対しても同様に、私たちには環境に適応しようという動きが自然と起こります。
しかし、社会環境の側がいびつでおかしければ、こちらの側が酔う(病む)ということは生じます。
例えば、とてもねじれた考えやコミュニケーションの仕方を持つ家族に囲まれて生活しているような場合などはそうです。
まともで、まじめであるほどに、そこに適応しようとすると「不適応」を起こしてしまう。
もっといえば、家族が持つねじれを、その利発で賢い子供の側が、家族のねじれを「整えよう」としてしまう。
例えば、親のねじれた発言を子どもが忖度して、意味が通るように“翻訳”したり、自分の感情を殺すようにして吸収したり、といったことはよく見られます。
親のおかしな行動を、マネージャーや執事のように先回りしてごまかしたり、取り繕ったりすることを半ば無意識に行うなどしたり。
歪んだ鏡に囲まれた部屋に住むがごとく、歪んだものに囲まれていれば、こちらの認知がそれに合わせるかのように歪んでしまいますが、前回の記事でも書いた「頭がねじれる」と、まさにそのような結果生じるのです。
(参考)→「トラウマ、ハラスメントによってどのように頭がねじれるのか?~連鎖して考えてはいけない」
それは、その人がおかしいから、ではなくて、その方が一番利発で、まともだからです。
たまたま、その人が引き受けてくれたおかげで、適当でいい加減でいられたりできたほかの兄弟(姉妹)は軽く済んだりすることもあります。
(あるいは、優等生として、歪んだ世界で優等生になったり、おかしいと思わないように誤適応したり)
おかしな環境で心が病む、というのは、その方がおかしいからではなくて、まともである証拠です。
しかし、本人は、適応できていない、あるいは症状を発症している自分がおかしい、弱い、病んだ人間だと捉えてしまう。
もちろん、そんなことは間違いです。
歪んだ鏡を見させられすぎて、ねじれてしまった頭を、常識の世界に戻って元に戻す必要があります。
元に戻す際に生じる課題は、「そのおかしな環境に対しても適応しなければならない」という偽の責任意識や、偽の義理の感覚(罪悪感)、自分への疑い(やっぱり病む自分がおかしいのだ、自分の中に問題があるのだ)が邪魔をする、ということです。
その邪魔自体、トラウマの柱の一つでありハラスメント(心理的支配、呪縛)によるものですが、まずは、知識レベルでよいので、自分は大丈夫だ、まともだからこそ苦しんでいるのだ、と知ることです。
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ



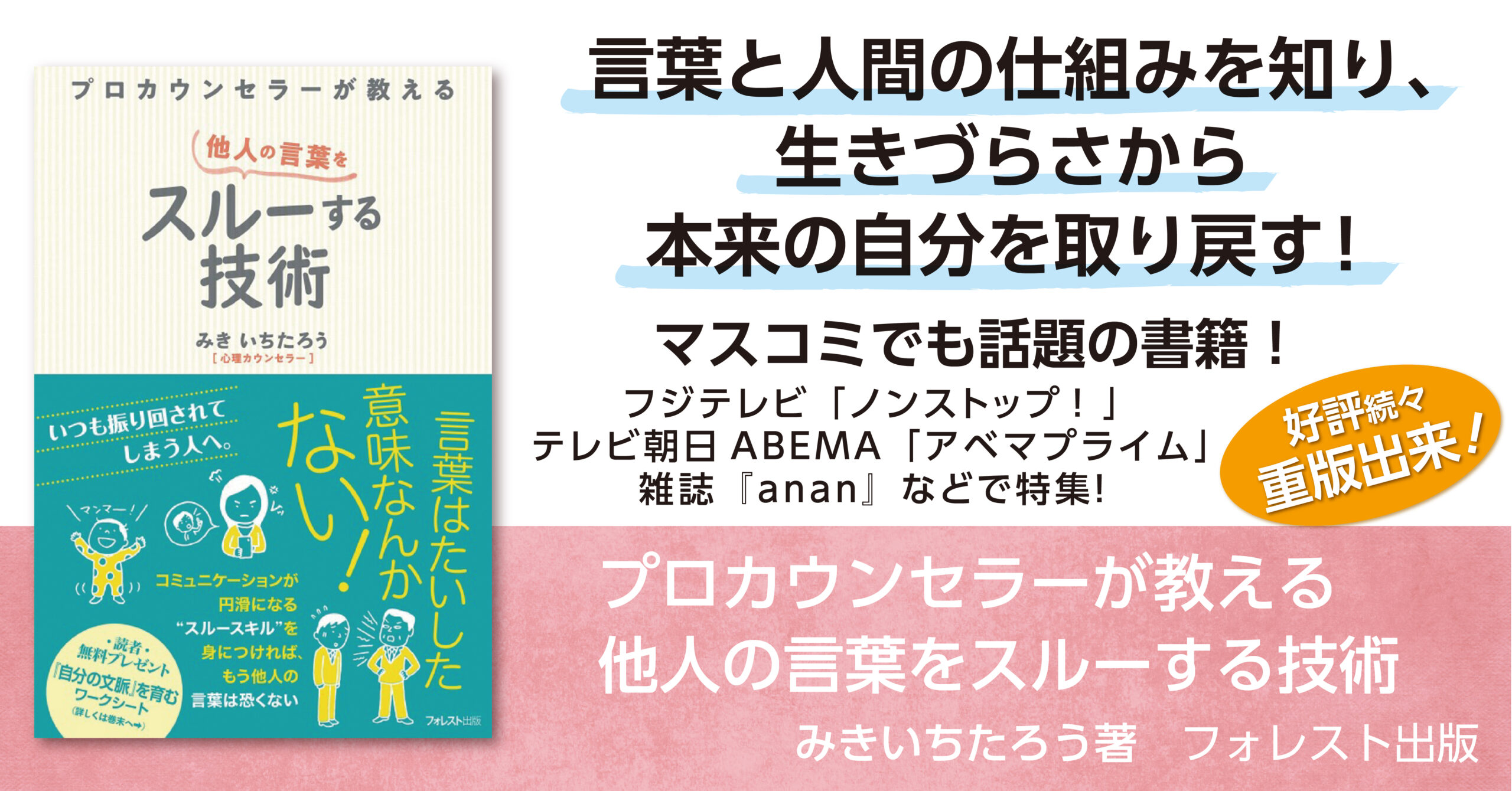
コメントを投稿するにはログインしてください。