今回は、前回ご紹介した『精神の生態学へ』(岩波文庫)に紹介されている母子の話についての続き、です。
ダブルバインドによって精神障害(統合失調症)を発症し、で入院していた息子のところに、問題の母親が見舞いに来ます。息子は入院によって体調はかなり回復をしていました。
しかし、母が来たことを喜んで息子が母の肩に抱き着くと、母は身をこわばらせます。
それで、息子がとっさに手を引っ込めると
母は「もう、私を愛していないの?」と言います。
顔を赤らめる息子に対しては母は、「そんなまごついてはいけないわ。自分の気持ちを恐れることはないのよ」といいます。
そうして、母が帰った後、息子は暴れ出し、ショック療法の部屋に連れていかれました。。。
もし、息子が「母は僕が肩に腕を回すと落ち着かないんだ。僕の愛情表現を受け入れられないんだ」とでも表現できれば、暴れ出すような破滅的な事態は起きず、状況は少しは改善したかもしれません。
しかし、息子は、強度の束縛(ダブルバインド状況)の中で、母親のコミュニケーションの真実を言語化することができない状況に育ってしまっているのです。
一方で母親は息子の状況にもっともらしい論評を加え、自分の解釈を息子が受け入れることを強要しています。
さらに、息子は医師からも「統合失調症」の烙印を押され、「暴れた」という事実もあるために、その診断は“医学的にも”合理的とされることになっています。
自分がもしこの息子だとしたらと思うと、本当に恐ろしい状況です。
前回も書きましたが、統合失調症として現れるか? 複雑性PTSD(発達性トラウマ)として現れるかは、単なる体質の差です。
パニック障害、解離性同一性障害、うつ病、依存症としてもあられることがあり、気質の違いによります。ベイトソンは、統合失調症の原因としてこれを書いていますが、複雑性PTSD(発達性トラウマ)でもそのまま当てはまります。
恐ろしいのは、では、この母の言動は、社会的に虐待と認定されるようなものなのか?といえばそうではありません。まったくもって“あいまいな”ものです。
しかし、この“あいまいな”虐待は、社会的認定されている虐待以上の恐るべきダメージをもたらしています。
では、ここで取り上げた見舞いの際の母のコミュニケーションをベイトソンが解説していますから、その詳細も紹介させていただきます。
●母親は、腕を引っ込めた息子の反応を「もう、私を愛していないの?」などとあげつらうことで、自分の拒絶を隠ぺいしています。
さらに、息子も母の非難を受け入れて自分の感覚、状況理解を否定しています。 (これが、母が帰った後で暴れたことにつながります。)
●「もう愛していないの?」という言葉からは、以下の含みがくみ取れます。
a)「わたしは愛するに値する」という前提。
さらに、
b)「お前は私を愛するべきだ。愛せないお前が悪い。それは間違っている」という非難の含み。
c)「もう」の一言が、「以前はわたしを愛していたのに、今は愛していない」という含みを添える。
それによって、息子が愛を表現できるか否か、ではなく、愛情を抱くことができるか否かに焦点が移ります。
しかし、息子は過去に母を憎んだこともあるのだから、この葛藤において母の優位は揺るがなくなります。
息子は過去も十分に母を愛せていなかったことに罪悪感を感じます。
d)「もう愛していないの?」と言うことで、つまり息子が母の肩を抱いたことについて「お前が今表現したことは、愛情ではなかった」という一方的なラベルを貼っています。
そのラベルを息子が認めるとき、これまで社会的に学んできた愛情表現の方法(肩を抱く、など)は愛情表現ではないと否定されます。
すると息子は、過去に自分が行った愛情表現が表現として不適切だったのだ、相手がそれを受け入れたと思えたことまでが疑わしい、と不安を感じるようになります。
ここで彼が経験するのは「支えの喪失」です。
過去の経験が自分の支えとしての機能を失ってしまう、疑わしいものになるということです。
●「そんなまごついてはいけないわ。自分の気持ちを恐れることはないのよ」
このメッセージには以下の意味を含んでいます。
a)「普通の人は自分の気持ちを表現するのにお前はそうしない、できていない。だからお前は他のきちんとした正常な人間とも違う」
b)「自分の気持ちを恐れることはない」ともっともなことを言い、「お前の感情自体は問題ない。問題はお前がその感情を容認できていないことだ」としていますが、しかし、自分が母に触れた時に母が示したこわばりが自分に現れた感情を母が容認しないと示している以上、彼は過去の葛藤に追いやられることになります。
母が勧めるように、自分の感情に恐れを感じないでいるならば、母への愛の感情も素直に表現して当然です。
しかし、そうしてしまえば、恐れているのは母のほうだを気づかずにはいられない。しかし、気づいてはならない。
息子はこれまで母との関係や母の幻想を壊してしまわないように、自分が感じた感情(つまり、母は私を拒絶している)を認めないようにして来たわけです。母は自分の欺瞞のために息子を協力させてきたのに、ここではそれがおかしいと非難をしているわけです。言葉では「自分の気持ちを恐れることはない」とキレイ事を言っていますが、構造としては、私の幻想と私との関係を壊すなとしているわけです。
この見舞いの場面では母に愛情を示さなければ母を失う、でも、示した愛情はおかしいとされる、自分の気持ちに率直になることは、母の幻想や関係を壊すためにできない、こうした解決不能のジレンマに息子はおちいっているわけです。
ベイトソンの解説は秀逸だと思います。
こうした構造の状況は、トラウマ、複雑性PTSDの相談において実際によくあります。
繰り返しになりますが、母の会話がもし音声で録音されていてもおそらくすぐには「虐待!」とは認定されないでしょう。よほど、家族関係やハラスメントの専門家が見なければ正しくアセスメントはしてくれません。
ましてや本人は呪縛の中にいますから、気が付きようもなく、しかし、心身に症状だけが生じていて、社会でもうまくいかず、人間関係も作れず、その“事実”から自分はおかしいと責めるようになります。
前回でも書きましたように、
「いや~、親がそれほどひどかったとは思えないんです・・」
「親のせいにするなんて自分がそう思いたいだけかもしれません??」
「実際に、社会でうまくいっていない自分のほうがおかしい。だって他の兄弟は何ともありませんし。。」などとなってしまうのです。
社会的にもあいまいだからこそ、それ自体が、第4、第5の拘束のメッセージともなりさらなる拘束となります。
まさに、あいまいなマルトリートメント(虐待)の恐ろしさです。
そして、あいまいなマルトリートメント(虐待)は、決して稀ではなく、そこここに存在しています。
母子に単純化していますが、これが、親族、学校、会社などでも様々な場面でも起こりえます。
生まれつきそうではないか?天才的!?と思うくらいに、絶妙のタイミングで私たちの些細な行動を弱点として取り上げて、あげつらう(ハラスメントをする)のが得意な人というのはいたりします。
あるいは、普通の会話、やり取りなのに、なんとも言えない嫌~な気にさせるような人などもいますし、皆様もそうした人に出会うことがあるのではないでしょうか?
(それは、もちろん生まれつきではなく愛着不安やトラウマによる不全感を抱えたことを土台として、その人の気質が合わさって生じるものです。)
そうしたことは表面では現時点では、虐待ともハラスメントとも、されないかもしれませんが、ベイトソンが明らかにした視点から精緻に分析すれば、それは、私たちを縛る欺瞞的なコミュニケーションなのです。
このことに対して私たち社会全体も、もうさすがに気がつかなくてはなりません。
不全感に基づく欺瞞的なコミュケーションについて賢くなり、明らかにしていく必要があります。
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ


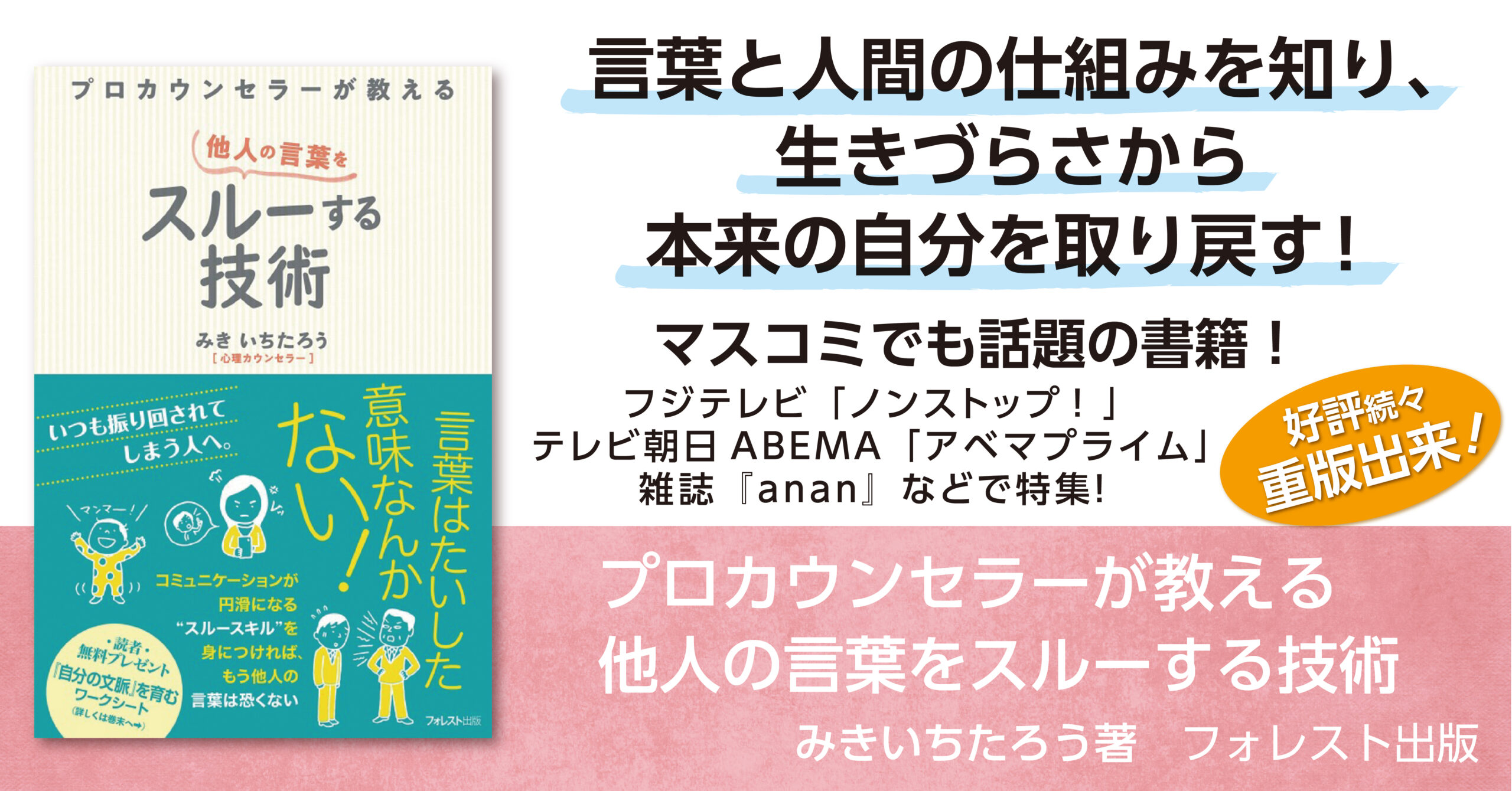
コメントを投稿するにはログインしてください。