例えば、現代であれば、親の介護といった問題で沸き起こる、「親孝行」や「家族愛」といったものです。
クライアントさんでも、親の介護に関連して、呪縛にかかるケースもよく見られます。
介護では、通常でも、安全基地(愛着の対象)であるはずの親が老いていく姿に認知がついていけず、また、「自分が頑張ればなんとかなる」という自己の規範から親に怒りが湧いてしまって、親にイライラ、暴言、暴力を振るってしまうこともよくあることとされます。
まさに、下記の本では、「親孝行の罠」として、そうしたことへの対処が書かれています。
プロの介護士は、自分の親の介護はできない、ということを一番最初に習うそうです。つまり、介護とは親自身の人生、日常の営みであり、子どもや家族が親孝行や家族愛といった規範から行うものではない、ということです。
「家族は、自分の家族の介護はできない」
これは、決して裏技でも、トリッキーな割り切りでもなく、介護の世界では“常識”“本質”とされることです。
しかし、「基本は家族が面倒を」というような俗な規範は世の中位を徘徊していますので、それにとらわれると「罪悪感」や「親への怒り」に心が呪縛されて、やられてしまいます。
先日の記事でも取り上げましたヤングケアラーとなってしましまう。
(参考)→「なぜ、家族に対して責任意識、罪悪感を抱えてしまうのか~自分はヤングケアラーではないか?という視点」
介護は社会の力を借りて行うものであり、自分の人生を捧げて行うものではありません。
子どもや家族は自分の人生や仕事を普通に過ごしながら、社会制度やプロの力を借りて行うことはできます。
まさに、専門家は「家族だけで行おうとしないでください」「介護のために仕事をやめたりしないでください」と啓蒙しています。
俗な規範にまつわる領域では、不全感(トラウマ)が触発されて正常な判断ができなくなります。
専門家に相談できず、あるいはしても見たいものしか見れず、「内を守り、外を疑う」というようなことになりがちです。
(参考)→「外(社会)は疑わされ、内(家)は守らされている。」
「他の家ではそうでも、うちだけは事情が違って、自分で面倒を見るしかないんです」と思っている場合ほど、ぜひ、お読みいただくとよいかと思います。
山中 浩之, 川内 潤「親不孝介護 距離を取るからうまくいく」日経BP
川内 潤 「わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう」日経BP
●よろしければ、こちらもご覧ください。

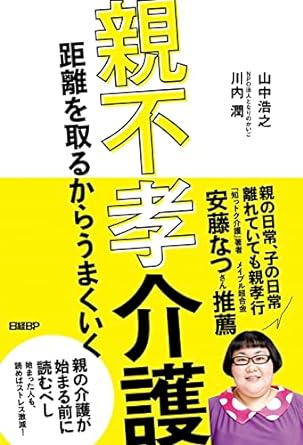

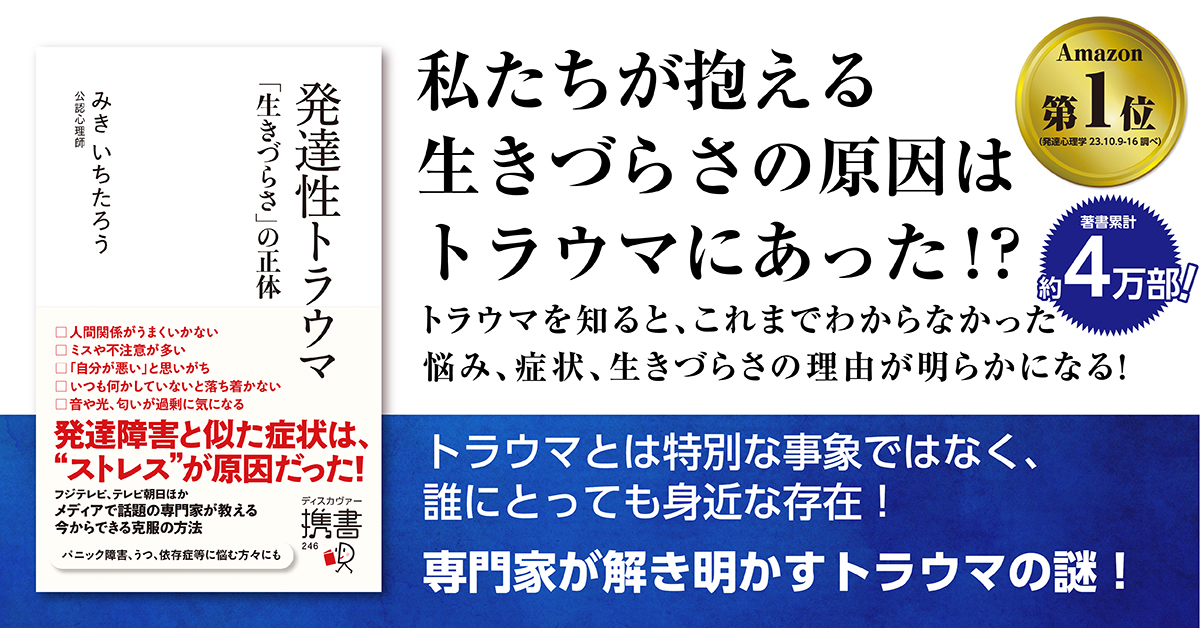

コメントを投稿するにはログインしてください。