トラウマを負うと、自分の感情や考えをストレートに出せなくなります。
他者の負の感情を飲み込んでいます。
その感情もシンプルなものではなく、とてもねじれたものです。
好きなものを好きとは言えない。
嫌なものをシンプルに嫌とはいえない。
不全感から発せられて、そこにもっともな理屈をつけている(≒ローカルルール)。
自分の中のトラウマからくる、不安や恐れ、そんなものが言語化できずに、自分の中ではいろいろな理屈をつけている。
それがとても深い思索のように感じている。
しかし、うまく言語化できない。
いざ、友人や知人に自分の苦しみを話してみても、思いの外言葉にできず「ふーん」とそっけなく返されたり、
(全然わかってくれない!! 共感力がない! 深みがない! とイライラしたり)
「そうなの。私の親が頑固でねー」なんて返されて、
(あなたが言うみたいにそんな簡単なものではない。一緒にしないでくれ!! と怒ったり)
残念ながら、トラウマを負った人の考えが深く、思索に富んでいるわけではありません。
そして、友人や知人が浅く、無理解というわけでもありません。
そっけない反応は健全なものだったりします。
トラウマというのは、ねじれた他者の感情や考えを飲み込まされることであり、さらに、経験、体験については言語化できない。
その結果、なにやら複雑な感情や思考が頭の中で渦巻いたりします。
それは決して奥深さを表しているわけではなく、単なる不全感の症状でしかありません。
なので、そこに共感をしてもなにも生まれません。
周囲が「なんで、そんなに難しく考えるの? こう(シンプル)じゃないの?」という反応は正しい。
小説家というのは、複雑な感情を言語にして描きますが、あれはあくまで職業として、エンターテイメントとして行っていること。
(小説家の中には自身が不全感を抱えていたり、精神をすり減らしてしまう人もいるかも知れませんが)
私たちは、哲学者や小説家みたいな複雑な感情を持つ必要はありません。
熱いものに触ったら、熱い でよいし、
冷たいものに触ったり、冷たい、でよい。
シンプル・イズ・ベスト。
複雑なものを作るのでも、シンプルの積み上げた先にありますから、最初から複雑にしていたら、積み上がるはずもありません。トラウマがもたらす積み上がらなさの要因の一つはここにもあるかもしれません。
最初から複雑なねじれた感情を入れて、熱いけど冷たい とか、熱いけど、熱いといってはいけない、とか、そんなことをしていると、だんだん自分の感情も言葉も奪われていってしまうのです。
これがまさにトラウマの状態。
まず主語は常に「私は~」ではじめて、自分の感情や考えはシンプルにする。
そして、「しかし~」とか、「ただ~」という接続詞をつかわない。
特に家族の影響を受けている人には、これが癖になっている人はとても多い。
本にも書かせていただきました「自分の文脈」を取り戻すためにも1人称で、短文で、常にシンプルに考えることはとても大事です。
●よろしければ、こちらもご覧ください。


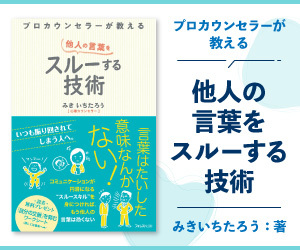
コメントを投稿するにはログインしてください。