現代の日本に生きているとあまりピンと来ないかもしれませんが、人間社会には、長く階級が存在してきました。
日本でも、「貴族」や「武士」といった分け方や、「士農工商」といった分類がありました。
現在でも階級のある国は少なくありません。
インドのカースト制度は有名ですし、知らない人も多いですが、イギリスは今でも階級社会です。
「ジェントルマン階級」や「労働者階級」という区分が存在します。
(ちなみに、ロンドンの土地は20数名のジェントルマンたちが所有していて、一般の人はそれを長期間賃貸にて利用しているそうです。)
こうしたことから、人間には、「階級意識」というものが原的に存在することは考えられます。
その「階級意識」が意味なく過剰に作用してしまうことで、自分を他人よりも下に置いたりしてしまって、「自信のなさ」や「うしろめたさ」といったものが根拠なく出てきてしまう、可能性があります。
一方で逆に、階級意識が機能低下していることも問題です。
結果として、他者を尊敬できず、他人の嫉妬を招いてしまう、というケースもあります。フランス革命の後の混乱は、秩序が壊れて嫉妬や恐怖が渦巻く、まさに狂気の時代でした。
逆の意味で階級意識が壊れてなくなるというのも恐ろしいことです。
なぜかというと、階級があるほうが、社会としては安定していたり、そこで生きる人の心情も分をわきまえて穏やかということがあります。
自分の住む小世界の中で勝者になれて、ほかの世界のことはまったく関心、関係がない(敬意を払うが、別世界)ということです。
階級がなくなっても、環境に伴った差が相変わらずあるにもかかわらず、機会の平等の結果であるということで個人の責任にさせられてしまい、理不尽さはさらに強まります。そのため嫉妬といった俗な感情が際立ってしまうのです。
インドのように因習となると問題ですが、階級意識があることが悪いことであるとは一概には言えません。
平等な社会のほうが差別はむしろ苛烈になることがあります。
愛着不安や、トラウマにさいなまれると、人に対して妙にへりくだったり、尊大になったり、他者からいじめられたり、ということが起きやすいのです。
その原因として「階級意識」がうまく働いていないのかも?
という観点から見るとなかなか面白いです。
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

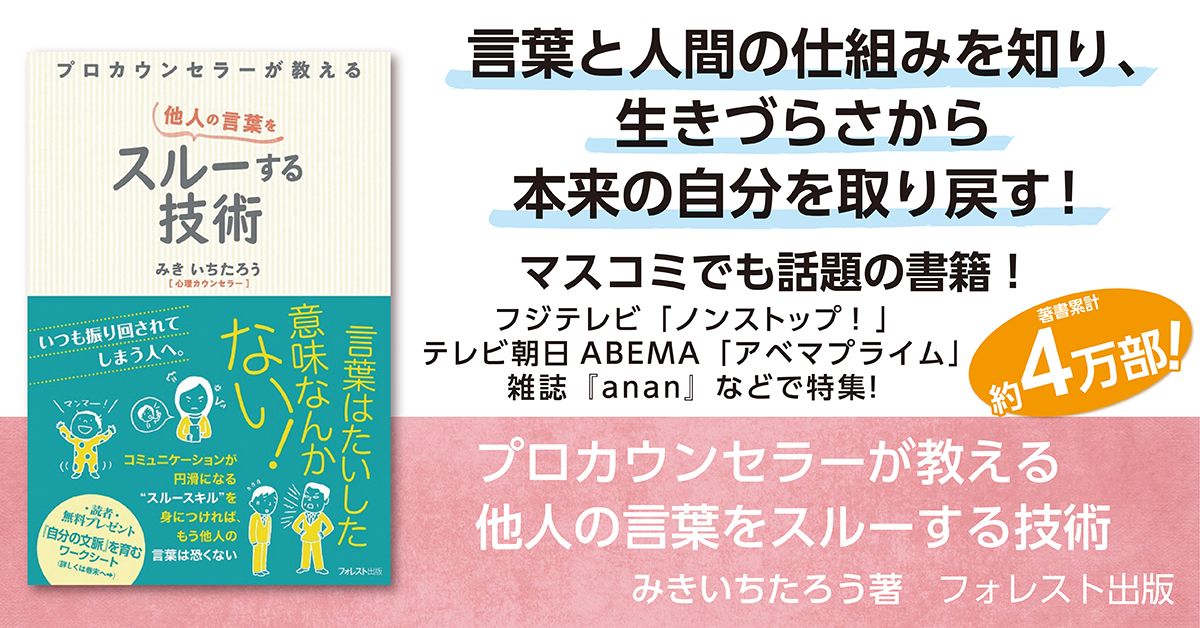
コメントを投稿するにはログインしてください。