親は、会社で言えば、ベテランマネージャーのように、暗黙のルールについてもポイントを把握している必要があるのです。
機能する家族では、メンバーが「弱くあること」が許されます。
そうして、弱さが都度、適切な形で消化される。
(参考)→「親や家族が機能しているか否かの基準~失敗(ハプニング)を捉え方、処理の仕方」
(参考)→「親や家族が機能しているか否かの基準2~ストレスへの対処」
これは、“弱い”メンバーに対してそうではなく、“一見強そうに見える”メンバーに対してもそうです。
結局、世の中でうまくいっている人、強い人でも、そうあることができるのは、多くの場合、誰かがその人の”弱さ”のケアをしているからです。
弱さを他人にケアさせることで成功や強くあることが成り立っている。
夫が、妻に弱さをケアさせていたり、
親が子どもにケアをさせていたり、
部活であれば、上級生が下級生にケアさせていたり。
会社であれば、上司が部下にストレスをケアさせていたり、
例えば、会社で、仕事ができるとされる人が結構イライラしやすく、部下がいろいろと気を回すことで、その人が仕事がうまくいくことが成り立っていたりします。
でも、当人たちはそのような構造には気がついておらず、イライラしやすいが仕事のできる上司と、怒られるその部下たち、というような感じになっている。
クライアントさんの問診を伺っていても、幼い頃、父親が暴れていた。あるいは、母親が気分屋ですぐにイライラして振り回されていた、というような話はよく伺います。
これらは歪に成り立っている機能であって、本来的なものではありません。
本来は、それぞれのメンバーが弱くあることが許される、そしてそれぞれに受け止める風土があります。
愚痴を言えたり、弱音を吐けることも大切です。
そこでは、世の中の実際(人はみんなそれぞれ弱い)も正しく理解されている。
ローカルルールによるマウンティングもない。
本当に意味で愚痴を言えて、受け止められて発散できれば、それらは解消されていきます。
前を向くことができます。
反対に、悪い形の場合は、ローカルルールによって拘束された価値観から変に強くあろうとして、あるいは、発散できなくて抑えてしまうようになり、結局、回り回ってその弱さは負担のかかる形で別の人(子どもやパートナーなど)がケアすることが必要になります。
(参考)→「ローカルルールとは何か?」
その押し付けられてケアの負荷は明らかにはされずに、ケアラーの側の不調とか、やる気が出ないとか、罪悪感というような形になり、以前の記事でも書きましたように、一見すると強者は何も問題がなく、弱者だけが問題があるからそうなっているという見え方になり、当人も何が問題かがわからなくなってしまうのです。
機能不全の状態では、そうした「感情の受容と交わり」がなされずに、ただ、一面的な対応しかされずに、本人の弱さだけが非難されたり、ということが行われます。
言っても無駄、となり、代替となる居場所を求めるしかなくなってしまうのです。
機能している家族では、そうしたことが生じにくいものです。
弱くあることが許され、ネガティブな感情も受容されます。
ムツゴロウさんが動物とじゃれ合うような感じで、「よ~しよ~し」とするような交わり感があります。
家族が機能しているか、自分の育った家族が機能していたか否か?という基準として、こうした、「感情の受容と交わり」があるか(あったか)どうかがあります。
(参考)→「<家族>とは何か?家族の機能と機能不全」
(参考)→「親や家族が機能しているか否かの基準2~ストレスへの対処」
(参考)→「親や家族が機能しているか否かの基準~失敗(ハプニング)を捉え方、処理の仕方」
●よろしければ、こちらもご覧ください。

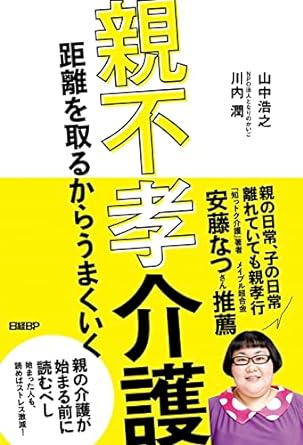

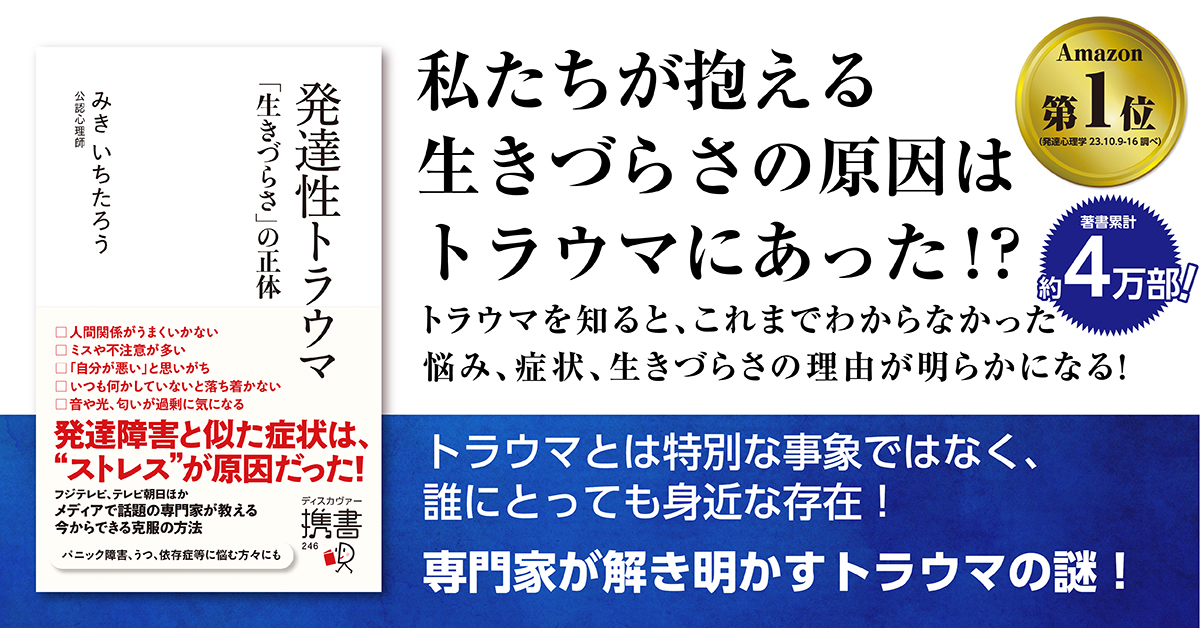
コメントを投稿するにはログインしてください。