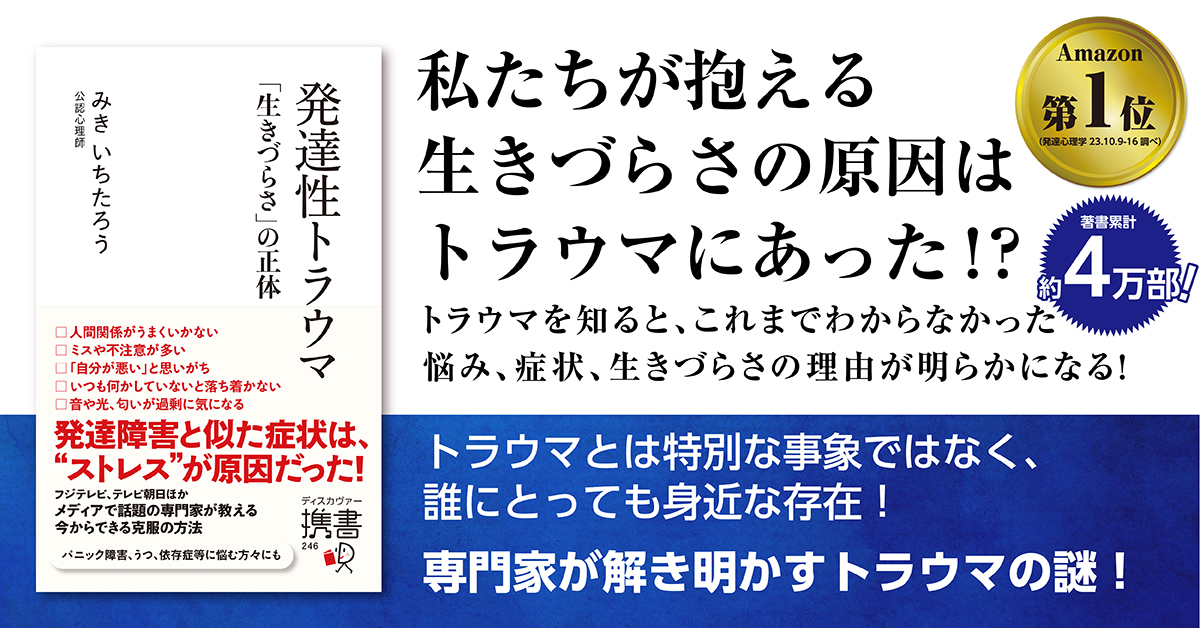「自他の区別」をつける、タイミングはいろいろありますが、最も大きなタイミングは「反抗期」です。
反抗期の効用は、親の価値観から離れる(「(心の中で)親を殺す」と言われる)こと、そしてそれまでの一元的な視点から、多元的な視点を身に着けることです。
トラウマを負った人の多くは、反抗期が無かったり、あるにはあったけど中途半端だったりします。
トラウマを負うと、「ニセ成熟」となり、精神的には妙にマセてしまったり、感情を回避したりということが起きています。
普通であれば、大人と戦って、乗り越えていく、ということですが、それをせずに、最初から頭の中で成熟してしまっていて、反抗期を回避してしまうことがあります。
すると、本人の中では「反抗期はあった(と思う)」となっていますが、本当の意味での反抗期とはなっておらず、親の価値観から離れているようで離れていない、「自他の区別」が付けられない、ということが起きてしまいます。
本人が反抗期と思っていたことは、親の価値観を早期に内面化して、頭の中で親を超えてしまっているだけだ、ということです。
さらに、家族が機能不全を起こしていれば、なお、それは強くなります。父親や母親は親としての機能を果たすことができずに、子どもから「見下され」たりします。
そうすると、反抗して乗り越える、というよりは、見下されて、「自分のほうがちゃんとしている」として、内実は、単に親の価値観を再編成しただけの中途半端な“反抗”になってしまうのです。
トラウマを負っているために、妙な理想主義となり、一元的なままになって、自分の価値観に合う者とはいいですが、合わない者とは折り合えない。
何か真実を知っていそうな雰囲気の人に支配されてしまったり、妙にした手に出てしまったり、不安になってしまったりするようになります。
成人になり、悩みを持つ方には、つらい養育環境で育った方も多いですが、 辛さの根底には、「親の価値観を相対化できない」ことがあります。それによって、自他の区別がつけれず、多元的にスイッチできない。
多元的とは、「自分は自分のままでいい」と思えることでもあります。親の価値観と離れないままだと、それが上手くいかないことが多いのです。
そうした方に、親と仲が悪いのだから「親との和解(親を肯定的に評価しましょう)」を提案するカウンセリングもありますが、このように考えるとおかしなことだということがわかります。
むしろ、反抗期を中途半端にし続けて、傷がぐずぐず膿み続けるような状態を続けることにもなりかねません。いったん、そうしたことには決着をつける、ということは大切なことなのです。
●適切な反抗を意図する
反抗期とは、成長期のホルモンバランスの乱れによるも のとされます。本能的なものとされます。
ただ、ホルモンの乱れでイライラする、という生物学的な機能と、親の価値観との決別という社会的な機能とは、別だと考えられます。
社会的な機能は環境が整わないと不発に終わることも多いのです。ただイライラするだけで終わってしまったり、それすら十分に感じられなかったり、といったことです。
反抗するためには、相対化する立脚点が必要になります。しかし、現代のような核家族で閉じられた社会の中では、親の価値観が覆ってしまっていて、反抗すらできないような状況にあることも少なくありません。
ダブルバインド(二重のメッセージによる呪縛)という現象がありますが、反抗することへの強い罪悪感であったり、反抗すること事態の親の価値観に沿うといったような巧妙な精神的支配をかけられていることで、うまく果たすことができないままでいることも多いのです。
また、イライラは激しいが、ただ暴言や暴力として表現されるだけで、立脚点がないために反抗期の機能は果たされていないというケースも多いです。
ただ、イライラ暴れていたから反抗期があった、という本人も記憶していますが、実はそれは反抗期ではなかった、ということがあります。
立脚点とは、かつてであれば、元服した先にある“社会”であったり、丁稚などで就く“しごと”であったり、カウンターカルチャーの価値観、家族外の年長者の価値観であったり、したのでしょう。
機能不全家族などの場合、家族がカルトのように閉じてしまうために、あるいは優等生になって家族を守ろうとするために、反抗が上手くいかなくなってしまうのかもしれません。
愛着(親子)の問題を解決する際に、和解や理解にばかり焦点が当てられますが、むしろ逆で、実際に家族との関係でお悩みの方は、“適切な反抗”をどうして達成するか?にこそ焦点を当ててみると、解決の糸口が見えるかもしれません。
●適切な反抗とはなにか?
反抗、というと文句を言ったり、暴言を吐いたりするようなことをイメージされるかもしれませんが、そのようなことではありません。
適切な反抗とは
・これまでの養育環境から受けた影響を相対化(自他の区別をつける)すること
であり、
さらに細かく言えば、
1.ダブルバインド(支配)に気づくこと
2.トラウマを解消すること
3.一元的な価値観の世界から、多元的な価値観の世界に移ること
(私は私、あなたはあなた)
です。
ダブルバインド(支配)とは、まさに正論(常識)をもとに相手を支配することです。
→「モラハラへの対策、治療のために知っておきたい6つのこと」
ご自身が罪悪感や自信の無さ、惨めさや苦しさを感じていたら、ダブルバインドやトラウマの影響が考えられます。
例えば、「自分が悪い」「自分はダメな人間だ」という根拠はどこから来るのでしょうか?
結局、ゴールポストを自在に動かす人(親、上司など)がいて、シュートが外させられて、「ダメな人間」という烙印を押されているだけなのです。
ダブルバインド(支配)とは、簡単に言えばゴールポストを勝手に動かされてしまって罪や罰を作らされてしまう行為を言います。
トラウマは、ダブルバインドから抜けられなくしている過去に追った傷、スティグマ(烙印)です。
→「トラウマ、PTSDとは何か?あなたの悩みの根本原因と克服」
ダブルバインド(支配)の理屈を聞いても、
「そうはいいますけど、私は“現実に”ダメな人間です。なぜかというとこんなことがあった、あんなことがあった・・・」
と当事者は思ってしまっています。
「こんなこと」「あんなこと」がまさにトラウマです。
普通であれば、記憶とともに流れていくものですが、それが流れず頭に残ってしまっていて「お前はダメな人間だ!」とささやき続けているのです。
さらに、一元的な価値観から多元的な価値観へ、というのはもうすこし簡単に言えば、「私は私」と思えることです。反抗期とはまさにこれを達成するためにあります。
例えば、仕事にしても人生にしても、正しい方法や価値観(反抗期の前は親の価値観)が一つだけあって、自分はそれが身についていない、知らない、と思ってしまうのが、一元的な価値観です。
一方、仕事も人生も人ぞれぞれ、価値観も取り組み方も違う、違ってていい、と思えるのが多元的価値観の世界です。相手が総理大臣であれ、社長であれ、あなたはあなた、私は私、と思えることです。
支配やトラウマを負っていると、一元的な価値観に染まってしまってそこから抜けられなくなってしまいます。
社会に出ても、支配的な人が寄ってきて「私はあなた以上のものを知っている」と誘惑してきます。
でも、世界は多元的だと知ると、見え方がガラッと変わります。
親も親で、あれはあれでいい、でも私は私、と思えるようになります。動じなくなるし、罪や罰もなくなります。
“適切な反抗”とは、本来生きる世界への入り口となります。
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ