筆者が、カウンセリングを提供していて、よく同じ職場のカウンセラーの先生等に冗談っぽくいうのは
「下手にカウンセリングを受けるくらいなら、運動するか、お祓いでも受けた方がよほどいいですけどね」
ということです。
(同じ職場のカウンセラーさんは冗談だと思って笑って聞いていますけど)
「お祓い」というのは、実際にそんな力があるかどうかは信じていませんが、ただ、親、家族などの環境から入れられた呪縛を解く手段としては、そんな方がいいかも?って本当に思います。「外部化」「簡便さ」といったブリーフセラピーの要素が入っています。
実際に、発展途上国では、統合失調症の治療でシャーマンなどが投薬に匹敵する効果を発揮したり、という報告があるようです。これも暗示の力ですね。
ブリーフセラピーでも、家族療法の東豊先生が、有名な”虫退治”という方法で、不登校など、家族の問題を解決したりしますが、まさにお祓いのような方法です。
ですから、お祓いに擬した方法(暗示)にはバカにならない効果があるとかんがえられます。
(もちろん、だから、いわゆるお祓いを推奨しているわけではありません。お祓いが持つ要素をセラピーに生かせば、というヒントという意味ですけれども。)
では、その要素とは何か?
「呪い」という言葉は、カウンセリングでは使いませんが、そういった方が適切なくらい、私たちに入っている暗示の力はものすごいものがあります。
それは、心理主義のポップ心理学や自己啓発のように、「コアビリーフが取れれば解決します」というように簡単ではありません。
暗示というのは、身体に刻まれるように食い込みます。身体とは、ホルモンや、遺伝子やそういったところまでです。
映画、アニメや漫画など、様々なストーリーでも主人公が苦しむ呪いは身体にも刻まれていて、腕とか体に黒い悪魔のような影があるような演出があったりして、考え方を変える、といった程度ではなかなかいうことをきいてくれません。
身体に刻まれている、という意味は、もちろん外科的なことではありません。
身体とは、一つは「発達」という視点。
人間は、親に育てられ、いっぱい暗示を入れられます。
ただ、反抗期で、その暗示を捨て「このクソババア、クソジジイ」と言って、神からの託宣だとおもっていたことが、単なる一意見に過ぎなかったことを知り、親の価値観を相対化して、成人へと成長していきます。
発達の中には、様々なイニシエーションをへて、成長のために必要な暗示を相対化していく機能があります。
しかし、トラウマなどで時間が止まり、「発達」が失調すると、暗示を脱ぎ捨てていく機能が損なわれてしまい、一時的でしかなく、偏った暗示がずーっと残り続けることになります。
反抗期がない、あってもただ不満をぶつけるだけで、本当の反抗期の機能ではなかった、ということはよくあります。
呪いを解く旅に出る神話などのストーリーは、人生の“発達”を示しているというようなことがよく言われます。
故郷から旅立って、様々な人との出会い、試練を経て、自立し、目的を達成する、大団円かと思ったら、そこに落とし穴があって、
本当の成熟を経ると、落ち着いた日常に戻ることができて・・・
途中には、裏切りとか、別れとかもあり、親(特に父)の影との格闘、
といったようなこともあります。
ユングといった人たちが、神話に着目したのも、暗示を解くためには慧眼だったかもしれません。
もう一つの視点は、「代謝」「ストレス応答」という視点。
外部からのストレスが来た場合に、それに対処して、自分を守る、ということを私たち人間は行っていますが、暗示が入ることで、それがうまくいかなくなります。
特にストレスは、社会、特に人間からもたらされます。
それへの対処は、身体も含めて、社会的な能力で行うものですが、「あなたは変だ」というような暗示が入っていては、しっかりと跳ね返すことができなくなります。足場がぐらついているところで重いものを持つような感じです。踏ん張れないのです。
さらに、長くストレスにさらされることで、オートマチックに動いて、助けてくれるはずのストレス応答のシステムが起動してくれず、頭ではわかっていても対処できず、さらに自分を責める悪循環に陥ってしまいます。
また、外から栄養を得て、老廃物を吐き出し、成長していく、といったこともうまくいかなくなる。
こうしたことも含めて解決することが必要で、単にビリーフとか考え方だけを変えても、根本的な変化は起こりません。
私たちも、暗示から抜け出るためには、座してセラピーを受けるだけではなく、社会に出て働き、人との出会いも経て、自分の原家族の価値観を相対化できる力を持つ必要もあるのだろうと思います。
(じゃあ、カウンセリング、セラピーは何をするの?というと、社会での旅が無事に終えられるようにサポートを行ったり、時には避難所となったりする。ファンタジーで回避させて旅を邪魔してしまうことはしない)
人によっては、がむしゃらに頑張って、社会で成果を上げて称賛されて、その実績をもって呪いを相対化させる、という人はたくさんいます。極端なのは、企業の創業者とか、芸能人などですね。
(ある程度成功したら、自分のBeingを癒すことをしないと、いつまでも成功を追い求めて破滅してしまうことになりますけれども。)
パーソナリティ障害、というのも、悪いことばかりではなく、それはそれで呪いをとくための未熟な一つの戦略ともいえます。自己愛性パーソナリティ障害などは、社会で成功するための爆発的なエネルギーを提供してくれますから。
ただ、上にも書きましたように、成功とともに並行して自分を癒して、成熟し、普通の社会に着陸しないといけませんけども。
トラウマを持つ方にとって、働くというのは、「怖い」といったイメージを持つ方も多いのですが、一方で、”仕事”というのは、呪いに立ち向かうための抵抗の拠点を提示してくれるものでもあります。
セラピーで間違った方向があるとしたら、愛着だとか、家族との和解とか、生き直しといって、家族に執着させるような方向性を持つようなケースです。
本当は、旅立たないといけないのに、それをかえって邪魔をして、主人公を“故郷”に縛り付けるような方向になってしまいます。
とくに現代は、核家族で、家族が閉鎖的で密着しすぎていて、親子関係の影響が濃すぎるのです。
親が支配的であるなら、親に執着して、態度を改めさせよう、というのは思うつぼです。本当なら、サッと切って、家を出ないといけない。
でも、まちがった家族道徳(ローカルルール)に縛られて罪悪感でうしろめたくなってしまったり、自分には自立などは経済的にはとても無理だと思わされて動けなくなってしまう。
(参考)→「親、家族についての悩みは厄介だが、「機能」としてとらえ、本質を知れば、役に立つ~家族との悩みを解決するポイント」
呪い(トラウマ)というのは、時間を止めてしまいます。
子どものような状態のままで止まってしまいます。
健全であれば起こるはずの人生のイニシエーションが起こらなくなってしまう。そうして、発達が不良になるので、呪いを負った人が抱える症状と、生まれつき発達障害の人との症状は相似形のように似るのです。
(発達性トラウマ症候群(いわゆるトラウマ)は、“第四の発達障害”と呼ばれます。)
セラピーのアイデアとしては、発達の過程をワークのように体験できる、といったことはありえます。催眠(ヒプノセラピー)でスクリプトを聴かせて、それで呪いを解く、というのは、まさに、短時間で“旅”を経験させる手法の一つです。うまくすれば、大きな効果がある。
(ただ、世にある催眠療法を受けたクライアントさんの感想を聞くと、なぜか効果はそれほど芳しくありません。何も変わらなかったという人は少なくない。催眠を受ければいいというものではなく、効果を出すためにはポイントがあるようです。)
あと、今ここに注目して、止まっている身体の時間を動かすような働きかけをする。トラウマケア(ストレス応答系へのアプローチ)というのはそのための手法です。
(参考)→「新たな療法の治療ポイントは「呼吸」(代謝):新しいトラウマケアのアウトライン」
暗示に縛られた状態というのは、自律神経や免疫、内分泌系などがが乱れている状態ですから、それを動かして、健全な代謝が起こるようにする。
運動、睡眠、食事ということがなぜ大事かといえば、止まっている身体の時間を動かす力があるから。
(参考)→「結局のところ、セラピー、カウンセリングもいいけど、睡眠、食事、運動、環境が“とても”大切」
セラピーとして着目するのは、やはり“呼吸”の力。呼吸をうまく活用して働きかけて、暗示によって縛られた身体を回復させていくことです。
お祓い、の持つ要素ということを考えると、人生のおけるイニシエーションを代行してくれる、また、無意識に働きかけて、うまく働かなくなった代謝を回復させるトリガーとなる、ということかもしれません。
カウンセリングは、あくまで科学的であることを志向しますから、
こうした要素をセラピーの内部に盛り込んで、難しいケースに挑んでいきます。
→「トラウマ、PTSDとは何か?あなたの悩みの根本原因と克服」
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

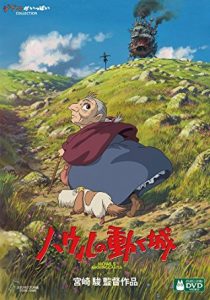

コメントを投稿するにはログインしてください。