臨床の専門家の中のある種の“常識”として、会社の社長や社会的に著名になるようなタイプの人には、「自己愛性パーソナリティ障害」の方が多い、というものがあります。
あれだけのエネルギーで何かを興そう、世の中を変えよう、というのは、ある種の自己愛のゆがみがエネルギー源になっていないとできない。
自己愛性パーソナリティ障害の口癖は「自分ならできる(自分が何とかしなきゃいけない)」というものです。
(参考)→「パーソナリティ障害の特徴とチェック、治療と接し方の7つのポイント」
彼ら彼女らは、Being(存在) が不安定ですから、Doing(行動),Having(成果) で埋め合わせようとガムシャラになる。
(「世の中に革新的なものを提供できなければ、自分には存在価値がない」「生きた証を残したい」というのですから)
安定型の人から見れば、「別にそのままでいいじゃないの」「あなたはあなたでしょ?」と言いたくなりますが、「いいや、納得しない!」と反論して、ブルドーザーのように進んでいく。
アップルの創業者のスティーブ・ジョブズなどはそんなタイプの典型といえます。
(アスペルガー障害ともとらえられますが)
芸能人やスポーツ選手にも多い。
そうした有名人たちが発する
「これからも挑戦を続けなければいけない」とか
「常にワクワクしています」
「自分はいつもエキサイティングなものを求めています」
といった発言は、まさにパーソナリティ障害のそれ、なのです。
(参考)→「パーソナリティ障害の特徴とチェック、治療と接し方の7つのポイント」
健康な人間とは”安定”を基礎とするものです。
常にワクワクを求める人間というのはおかしい。
いつもエキサイティングなもを求めるのは中毒です。
前回も書きましたが、テレビのドキュメンタリーで、海外やリゾートでくつろいでいる姿がありますが、裏を読めば、海外やリゾートでもなければくつろげないコンディションであるということ。
(有名なので、日本ではなかなかくつろげない、という事情もあるとは思いますが)
少し前にTV番組で、
かつて一世を風靡した経営者が海外で、様々なレジャーを楽しんでいる姿を追跡して、あたかも、「常識の縛られず、心から楽しめるすごい人」みたいなイメージで放送していましたが、臨床家から見るとかなり疑問符がつきます。
もちろん、有名人でも安定型の方、健康な方はいらっしゃいます。
ただ今度は、TVや出版社が演出を加えてしまうので、実像が見えにくくなる。
そうしたTVや書籍で演出された有名人たちの姿や発言を見て、真に受けてはいけない。
世の中には、イメージや幻想をもとに商売をする人がたくさんいる、ということです。
真に受けてしまうと、わけが解らなくなる。
例えば、クライアントさんからよく聞くお悩みで、
「いつもワクワクしていなきゃ、とおもうんですが、できないんです」
「普段の生活を楽しめないんです」とか
「やる気が続かないんです」
というものがあります。
もし有名人や、自己啓発のグルを演じている人たちに憧れたり、真似しようとしたり、自分とを比較してしまっているなら、なにが普通で当たり前なのかがわからず、おかしくなってしまいます。
やる気は何もなければ起きないもので、いつもワクワクしているとしたらそれは病気です。普段の日常とは退屈なもので、幸福とは退屈な中にじんわりと漂ってくるもの。
健康な体には波があって、恒常性を維持しながらテンションが上がるときは上がり、何もなければリラックスしているものです。
やる気もアップダウンするものだし、ワクワクというのはイベントや祭りの時だけ。
それが普通のことなのです。
有名人には、その人そのものや演出の中にパーソナリティ障害的な要素がかなり含まれる、ということを念頭に置いておいて、見本にするにしても、そうした要素はうまく除いて、エッセンスをとらえる必要があります。
作り出された幻想に巻き込まれず、比較もせずに、そうしたものから少し距離をとってみると、自分のペース、本来いる場所が見えてきます。
(参考)→「トラウマ、PTSDとは何か?あなたの悩みの根本原因と克服」
●よろしければ、こちらもご覧ください。
・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

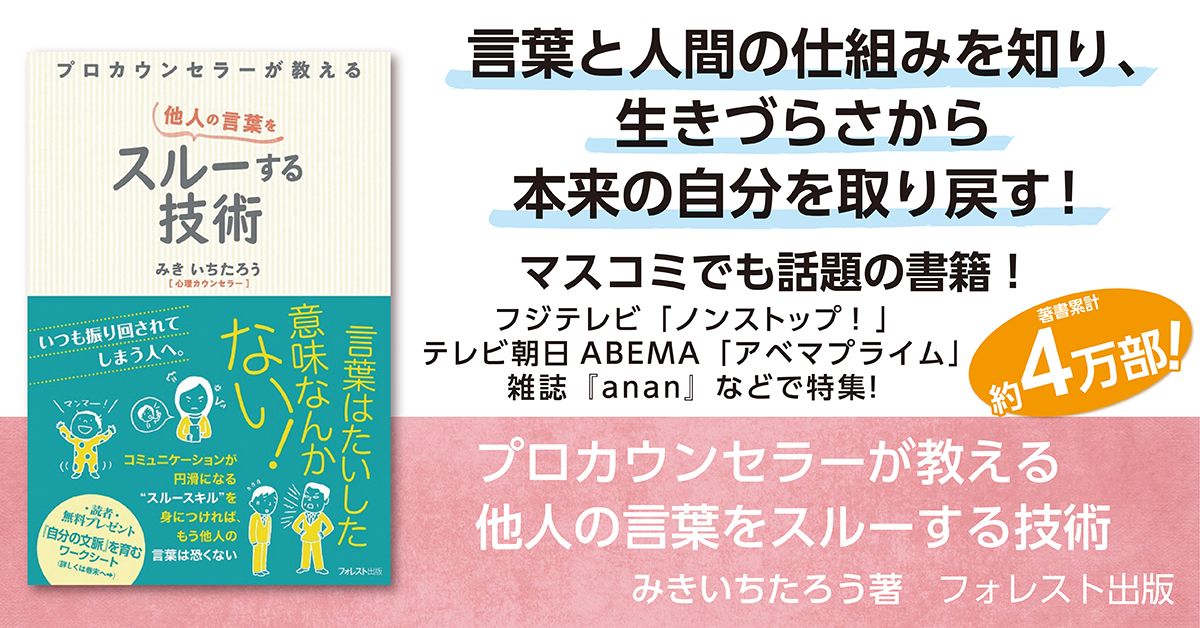
コメントを投稿するにはログインしてください。